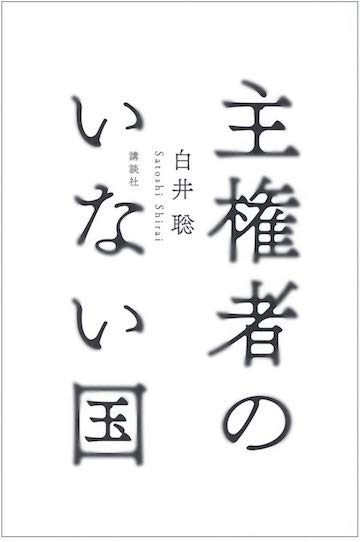◎ここ数日花冷えというか冷え込みが厳しいですが、いつもより春の花の開花が早いようです。バラもクレマチスもつぼみが膨らみかけています。ビオラは花盛りです。


 ◆東洋経済オンライン掲載全文をコピーさせていただきます。著者の最新刊の「主権者のいない国」の内容を把握するために予備知識として理解しておいてほしいという思いで書かれているようですが、原発事故から10年経って、コロナ禍中にある私たちが2度の体験を通して白井氏が言いたいこと「敗戦を認めようとしない為政者に依る政治が続き、反知性主義の蔓延る現在、コロナ対策がまともにできない政治が続いている」という現状認識を訴えて、後段、最新著作の内容に入ります。
◆東洋経済オンライン掲載全文をコピーさせていただきます。著者の最新刊の「主権者のいない国」の内容を把握するために予備知識として理解しておいてほしいという思いで書かれているようですが、原発事故から10年経って、コロナ禍中にある私たちが2度の体験を通して白井氏が言いたいこと「敗戦を認めようとしない為政者に依る政治が続き、反知性主義の蔓延る現在、コロナ対策がまともにできない政治が続いている」という現状認識を訴えて、後段、最新著作の内容に入ります。
🔲原発事故からの10年とコロナの2年が見せてくれるものはあの戦争の「無責任の体系」の繰り返し。この辺りまで一気に読めます:
引用元:10年前の「反復」がもたらした日本のコロナ危機 | 読書 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 (toyokeizai.net)
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
10年前の「反復」がもたらした日本のコロナ危機
「中止だ中止」と言えない主権者と無責任の体系
破滅の淵を想起する
本書が店頭に並ぶ頃、あの3.11からちょうど10回目の春を私たちは迎える。この10年は、私個人にとっても、日本という国にとっても激動の歳月であった。本来政治思想史の研究者である私は、3.11をきっかけとして『永続敗戦論――戦後日本の核心』(2013年、太田出版/2016年に講談社+α文庫に収録)を書き、それ以降、現代日本政治に関する時事的な発言に踏み込むことになった。
 それは、研究者・文筆家として思いがけない成り行きであったが、私を駆り立てたのは、「何とかしてこの国の崩壊を止めなければならない」という思いだった。
それは、研究者・文筆家として思いがけない成り行きであったが、私を駆り立てたのは、「何とかしてこの国の崩壊を止めなければならない」という思いだった。
10年前、日本を襲ったのは、文字どおりの激震だった。巨大津波による被害だけでも筆舌に尽くしがたいものがあるが、経験したことのない種類の惨禍をもたらしたのは福島第一原子力発電所の過酷事故だった。
当時の不安な気持ちを思い起こすだけでも胸苦しさすら感じるが、それでもやはり振り返っておくべきだろう。私たちが東日本壊滅という事態を避けることができたのは、ひとえに《運がよかった》からであった。
多くの危険きわまる事象のうち最も危険であったのは、4号機の核燃料プールの件だった。そこには1331体の使用済み核燃料が納められ、うち548体はつい4カ月前に原子炉内から引き抜かれたばかりの、高温の崩壊熱を放つものだった。そのプールに注水できなくなった。注水できなければ当然、プールのなかの水は核燃料の崩壊熱によって蒸発し、燃料がむき出しになる。アメリカは懸念を深め、原子力規制委員会のグレゴリー・ヤツコ委員長は「プールの水は空だ」と発言した。
使用済み核燃料は、劇物中の劇物である。もしそれがむき出しの裸の状態で置かれていたら、周りの人間は即死するほどの高線量を放つ。ゆえに、4号機の核燃料プールの水が空になり、むき出しになった使用済み核燃料が溶け出すということは、誰も福島第一原発に近づけなくなるということ、したがって、メルトダウンの事故処理も全くできなくなること、を意味した。
だから、当時の菅直人政権は、最悪のシナリオとして、首都圏を含む東日本全体の壊滅を想定したというが、それは何ら大袈裟なものではなかった。この事態は、東日本壊滅というよりも、日本壊滅と考えたほうが適切であろう。また、日本にとどまらず、世界全体の自然環境に対する影響の観点からすれば、文明の終焉すらもたらしかねない事態だった。
この危機を救ったものは、《偶然》だった。3月16日の夕刻、4号機上空を飛んだヘリコプターからの撮影により、核燃料プールに水があることが確認される。なぜ、ないはずの水があったのか?
それは、核燃料プールに隣接する「原子炉ウェル」という部分に張ってあった水と、原子炉ウェルにつながる「ドライヤー・セパレーター・ピット」という部分の水が、プールに流入したためだった。原子炉ウェルとプールの間には仕切り板があるのだが、地震の振動などにより仕切り板がずれて流入したとみられる。そして、われわれがとりわけ「幸運だった」というのは、原子炉ウェルは、通常水が満たされる場所ではないからだ。なぜそこに水があったのか?
 事故前年の末に、4号機では原子炉のシュラウドと呼ばれる部分の付け替え工事が始まっていた。このシュラウドは、長年の使用により放射化しているために、それを通過させる原子炉ウェルには水が張られていた。しかも、その水は、2011年3月7日に抜き取られるはずだった。そうならなかったのは、シュラウドを切断する際に使用する治具に設計ミスが発見され、付け替え工事の工期が延びていたためであった。
事故前年の末に、4号機では原子炉のシュラウドと呼ばれる部分の付け替え工事が始まっていた。このシュラウドは、長年の使用により放射化しているために、それを通過させる原子炉ウェルには水が張られていた。しかも、その水は、2011年3月7日に抜き取られるはずだった。そうならなかったのは、シュラウドを切断する際に使用する治具に設計ミスが発見され、付け替え工事の工期が延びていたためであった。
もしもシュラウド交換工事が2011年3月11日に重ならなければ、そして工期延長がなければ、あの最悪のシナリオが招き寄せられたのである。私たちは、文字どおりの破滅の間際にいた。このことは、どれほど強調しても足りない。
まるで狂人と正常人のやり取り
かつ恐るべきことに、この状況の深刻さをその当事者たる東京電力の上層部は、まったく理解していなかった。3月13日昼過ぎの時点で原子炉に注入する淡水がなくなり、吉田昌郎福島第一原発所長は、海水を注入するほかないと報告した。その直後の東電本社と現場とのテレビ会議の模様が後に報道されるが、そこで東電幹部から発せられた言葉は耳を疑わせるものだった。
「いきなり海水っていうのはそのまま材料が腐っちゃったりしてもったいないので、なるべくねばって真水を待つという選択肢もあるというふうに理解していいでしょうか」
 この幹部が懸念したのは、海水を注入された原子炉が使用不能になることだった。吉田所長は「理解してはいけなくて、(中略)今から真水というのはないんです。時間が遅れます、また」と即座に返しているが、この会話は狂人と正常人のやり取りに聞こえる。メルトダウンはもう間近に迫っていた。そんな原子炉を二度と使えるはずがない。
この幹部が懸念したのは、海水を注入された原子炉が使用不能になることだった。吉田所長は「理解してはいけなくて、(中略)今から真水というのはないんです。時間が遅れます、また」と即座に返しているが、この会話は狂人と正常人のやり取りに聞こえる。メルトダウンはもう間近に迫っていた。そんな原子炉を二度と使えるはずがない。
そして何よりも、この瞬間は、日本が破滅するかどうかの瀬戸際にあったのだった。東電幹部の言葉からは、そのような認識と切迫感が一切感じられない。「原子炉が使えなくなると我が社に何百億円も損が出る」という懸念があるだけだ。要するに、この人物は、「日本が終了してしまうこと」と「東京電力という会社が何百億円か損失を出すこと」とを天秤に掛けてどちらが重大であるのかを判断できなかった。
否、東電の損失すら考えていなかったもしれない。大失態を起こしてしまった原子力部門に属する自分の出世の困難を思っていたのかもしれない。かかる人物を形容するにあたり、「狂人」以外に適切な言葉を私は知らない。
危機を適切に認知できない人々には、同時に責任感もモラルもない。ただひたすら空っぽである人たちからなる集団が、この国の「選良」として君臨してきた挙句に、あの事故を起こした。なぜ、日本はこんな国でしかないのか、こんな社会でしかないのか。
その根源を見定めようとするならば、「あの戦争(第2次世界大戦)の未処理」という問題にまで遡らなければならないという確信に基づいて、私は『永続敗戦論』を書いた。あの事故における東電幹部や経産省関係者(原子力安全・保安院)、さらには「原子力ムラ」の御用学者たちの姿は、丸山眞男が昭和のファッショ体制を指して述べた「無責任の体系」そのものであったからだった。
 だから、福島第一原発の事故は、未曾有の経験であったのと同時に、見慣れたものでもあった。つまるところ、3.11が暴いたのは、「戦後日本はあの戦争への後悔と反省に立って築かれてきた」という公式史観の虚偽性だった。私たちの社会が本当に後悔・反省しているのなら、「無責任の体系」は克服されていなければならない。
だから、福島第一原発の事故は、未曾有の経験であったのと同時に、見慣れたものでもあった。つまるところ、3.11が暴いたのは、「戦後日本はあの戦争への後悔と反省に立って築かれてきた」という公式史観の虚偽性だった。私たちの社会が本当に後悔・反省しているのなら、「無責任の体系」は克服されていなければならない。
しかし現実には、それは社会のど真ん中で生き延びてきたことを3.11は明らかにした。ならば、なぜかくも無反省でいられるのか。その根源的な理由は、日本人が本当はあの戦争で敗北したことを認めていないというところにあることを私は『永続敗戦論』で主張し、かかる歴史意識を「敗戦の否認」と名づけた。
歴史観や歴史意識は、その社会の質に関わり、ひいては私たちの生き死にに関わる。3.11が突きつけたのは、私たちの社会は解体的な出直しを必要としているという事実にほかならなかった。最近やたらと増えている分断批判業者の連中は認めたがらないようだが、この時以来、日本社会は真二つに分裂した。それは、この事実を受け止める人々と何としてでも受け止めない(否認する)人々との分裂である。
 どちらが多数派であるかは言うまでもない。ちょうど『永続敗戦論』の原稿を書いていた2012年12月の総選挙で第2次安倍晋三政権が成立し、そこで出来上がった権力構造が現在にまで続いていることは、まさにこの「敗戦の否認」という歴史意識から日本人全般が脱していないばかりか、そのなかにさらに深くはまり込んでいることの証明である。というのも、安倍晋三こそ、政治の世界で「敗戦の否認」の情念を代表する人物にほかならないからだ。
どちらが多数派であるかは言うまでもない。ちょうど『永続敗戦論』の原稿を書いていた2012年12月の総選挙で第2次安倍晋三政権が成立し、そこで出来上がった権力構造が現在にまで続いていることは、まさにこの「敗戦の否認」という歴史意識から日本人全般が脱していないばかりか、そのなかにさらに深くはまり込んでいることの証明である。というのも、安倍晋三こそ、政治の世界で「敗戦の否認」の情念を代表する人物にほかならないからだ。
ゆえに、この期間が日本史上の汚点と目すべき無惨な時代となったのは、あまりにも当然の事柄である。虚しい歴史意識は、社会を劣化させ、究極的にはその社会を殺し、場合によってはそこに生きる人間を物理的に殺す。
3.11の反復としての新型コロナ危機
そして、まさにそのような「場合」にいま私たちは立ち会っている。言うまでもなく、新型コロナウイルスによる危機のことである。
 この1年間展開してきた光景は、10年前の光景の再上演のようなものだ。すべてが後手後手であり遅い。根拠なき楽観主義による事態の過小評価。政治に忖度する専門家という名の御用学者。懸命に踏ん張る現場と無能な司令官。「新型コロナウイルス感染症を克服した証しとしての東京五輪開催」(菅義偉首相)とやらは、福島第一原発の事故後に原子力ムラがぶち上げた「世界一安全な日本の原発」を世界中に輸出するという空理空論の反復である。無論、これらの末期症状は、破滅の瀬戸際に追い詰められてもそれをも否認してきた私たちが必然的に招き寄せたものにほかならない。
この1年間展開してきた光景は、10年前の光景の再上演のようなものだ。すべてが後手後手であり遅い。根拠なき楽観主義による事態の過小評価。政治に忖度する専門家という名の御用学者。懸命に踏ん張る現場と無能な司令官。「新型コロナウイルス感染症を克服した証しとしての東京五輪開催」(菅義偉首相)とやらは、福島第一原発の事故後に原子力ムラがぶち上げた「世界一安全な日本の原発」を世界中に輸出するという空理空論の反復である。無論、これらの末期症状は、破滅の瀬戸際に追い詰められてもそれをも否認してきた私たちが必然的に招き寄せたものにほかならない。グローバルな感染拡大の始まりから約1年を経て知見と経験が蓄積したいま、何をしなければならないか、何をしてはならないか、かなりはっきりしてきている。新型コロナウイルスの性格上、PCR検査を中核とする検査体制を大幅に拡充し、できるだけ多くの感染者を捕捉し、隔離しなければならない。
しかも、検査における偽陰性や偽陽性の問題をクリアするために、また医療や介護の関係者といったリスクの高い人々のためには、頻回検査が必要である。これを実行するためには、大々的な検査・隔離体制の確立と運用が絶対的に必要である。そしてそのためには、保健所だけでなく民間のPCR検査機関、大学等を有機的に組み合わせた体制を構築せねばならない。
 しかるに、いまだにこの体制ができておらず、国家による体制構築の決断さえなされていない。初期に定められた検査抑制の方針が今日でも亡霊のように漂っている。日本で新型コロナ感染がはじまったとき、PCR検査体制の不備を理由に厚労省が検査抑制の政策を採ったことには一応の合理性があったのかもしれない。
しかるに、いまだにこの体制ができておらず、国家による体制構築の決断さえなされていない。初期に定められた検査抑制の方針が今日でも亡霊のように漂っている。日本で新型コロナ感染がはじまったとき、PCR検査体制の不備を理由に厚労省が検査抑制の政策を採ったことには一応の合理性があったのかもしれない。
だが、いまとなってはこの体制の構築ができていないのは、恥ずべきことだ。とりわけ、ほかならぬ日本のメーカー(PSS社)が開発した全自動のPCR検査機器が外国で使われ同社が感謝状を受けている一方で、国内では導入が遅々として進まず、「手作業」(!)による検査が続いているという光景は、一体何なのか。
PCR検査体制の拡充を阻止してきた
帰責されるべきは、政権与党や政府首脳のみではない。思えば、2020年5月4日には、安倍首相もPCR検査の実施体制が意図したとおりに拡大していない現実に言及して、「目詰まりがある」と不満を述べていた。
そこで興味深いのは、新型コロナ対応・民間臨時調査会(コロナ民間臨調)がまとめて2020年10月に公刊されたレポート、『調査・検証報告書』に収録された厚労省の内部資料、「(補足)不安解消のために、希望者に広く検査を受けられるようにすべきとの主張について」である。
この資料は、政権中枢へのレクチャーのために作成されたのではないかと推せられるが、PCR検査における偽陰性・偽陽性の問題を強調して、検査の拡大が医療崩壊やさらなる感染拡大を招くと主張し、「従って、医師や保健所によって、必要と認められる者に対して検査を実施することが必要」と結論づけている。これはすなわち、厚労省の内部の人間が政権中枢に働きかけてPCR検査体制の拡充を阻止してきたことの証拠である。
これが「目詰まり」の本体ではないのか。厚労省、とりわけその医系技官たちの保健所に対する権益維持の意図が、保健所によるPCR検査と情報の独占(したがって、検査拡大の拒否)を動機づけているとの見解を医師の上昌弘が述べているが、この指摘には説得力がある。
 いずれにせよ、「目詰まり」は実在し、それを取り除くのが政治の仕事だ。問題はPCR検査体制の拡充だけではない。すでに何カ月も前から、新型コロナ治療を行う病院の集約化(コロナ病棟専門化)の必要が訴えられているが、これも進んでいない。水際対策もいまだ不徹底である。政府の新型コロナ対策のうちおおむね上手く機能していると評価できるのは、雇用調整助成金のみではないだろうか。
いずれにせよ、「目詰まり」は実在し、それを取り除くのが政治の仕事だ。問題はPCR検査体制の拡充だけではない。すでに何カ月も前から、新型コロナ治療を行う病院の集約化(コロナ病棟専門化)の必要が訴えられているが、これも進んでいない。水際対策もいまだ不徹底である。政府の新型コロナ対策のうちおおむね上手く機能していると評価できるのは、雇用調整助成金のみではないだろうか。
菅は、これらの当然の仕事から逃避し、「先手先手」、「全力で対応」、「安心と希望を届ける」等々の陳腐で抽象的なフレーズを繰り返すのみで、国民の絶望感を醸成している。その一方で、入院を拒否する感染者を逮捕し懲役を科するなどと言い出す。入院したいのにできない感染者が激増するなかで、である。政権はコロナ対策を諦め、面白いブラックジョークをつくることに専念し始めたかのようだ。
そして、結局のところ新型コロナを制圧できるのは、行動抑制である。この政策の困難は、必要となる補償の大きさもあるが、それ以上の本質的困難は、国民の政府への信頼が必要であることにあり、まさにこれこそが、現在の日本政府が日々刻々と失い続けているものである。また、これまでの無為無策・無能に鑑みれば何ら驚くべきことではなく当然のことだが、切り札の期待がかかるワクチンの供給・接種も到底速やかにはいきそうにない。
かくして、いまや諸国の新型コロナ対策ははっきりと明暗が分かれつつあり、対策が奏功した国々では、日常生活が通常の状態に近いものに戻りつつあり、経済停滞も回復しつつある。そのなかで、日本の状況はアジア太平洋地域で最低の水準にある。本格的なコロナ対策の体制がいまだ構築されていないことはすでに述べた通りだが、しかもアクセルとブレーキを同時に踏むような政策を延々と続け、その誤りを認める気配さえない。このままでは、近い将来、世界の多くの国と地域がコロナ危機から脱するなかで、日本は脱出できないという状況すら想定できるだろう。
 そうした情けない立ち位置、嘆かわしい状況は、まさに日本社会の質が招き寄せたものにほかならない。
そうした情けない立ち位置、嘆かわしい状況は、まさに日本社会の質が招き寄せたものにほかならない。
例えば、ここ10年ほどのあいだ顕著になった、日本社会の反知性主義的傾向は、新型コロナ対策の失敗においても如実に現れている。専門知の軽視、優れた専門家ではなく、政治に阿る専門家の登用、検査抑制をめぐる議論では、「権威主義的性格」の持ち主が一見もっともらしい「知識」をひけらかして世論を混乱させたその悪影響は甚大なものだった。これらすべては、莫大な予算が投じられた「対策」を無効化し、本来避けられたはずの犠牲を増やし続けている。
しかしながら、それはやはり不可避でもあったのだ。われわれは、あの10年前の破滅の淵から何も学ばなかったことの結果を引き受けさせられているのにすぎないのだから。
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
『主権者のいない国』の構成
本書『主権者のいない国』は、「統治の崩壊」と言うべき段階にまで陥った日本の政治、そしてそれを必然化した日本社会について、折に触れて私が書いた分析・考察の文章をまとめたものである。2013年の『永続敗戦論』以来、『「戦後」の墓碑銘』(2015年、金曜日/増補版が2018年、角川文庫ソフィア)、『戦後政治を終わらせる――永続敗戦の、その先へ』(2016年、NHK出版新書)、『国体論――菊と星条旗』(2018年、集英社新書)などを世に問うて、危機の分析を続けてきた。本書はその最新版である。
第1章には、昨年9月に退陣した第2次安倍晋三政権とその後継たる菅義偉政権に関する論考を集めた。『永続敗戦論』と『国体論』で分析してきたように、2012年の総選挙以来継続してきた自公連立長期政権は、日本の「戦後」という時代がその土台喪失にもかかわらず無理矢理に維持されてきた、その矛盾の爆発的な露呈の表現であり産物である。本章では、その矛盾の本質を提示し、矛盾がいよいよその最終的な自己破壊の過程に入り込んでいる様を分析する。
第2章は、新自由主義社会批判を主題としている。第1章で示唆されるように、悲惨な政治を支えてきた基盤は、結局のところ現代日本社会それ自体の悲惨さであり、日本人自身の悲惨さである。ではなぜ、社会は劣化してしまったのか。私は、2020年に『武器としての「資本論」』(東洋経済新報社)を刊行したが、同書はマルクス『資本論』のガイドであると同時に、新自由主義批判を企図している。
同書に含まれる重要な主張は、新自由主義は、単に政策を支えるイデオロギーではないということだ。今日それは、一種の文明の原理と化し、したがって人々の魂のなかに入り込んでいる。その諸相を、新自由主義の同伴者たる反知性主義に対する分析とともに、本章は提示する。
第3章には、『国体論――菊と星条旗』に深く関連する論考を集めた。『国体論』刊行の約1年後に、平成から令和への改元が行われた。改元の過程で際立っていたのは、安倍政権による改元・元号の「私物化」だった。この恐れを知らぬ振る舞いが平成の天皇(現上皇)の思慮深い言動と著しい対照を成すなかで、平成時代は終わった。
他方、世論は天皇自身の異例の意思表示による生前退位(譲位)という事件の意味を深く受け止めることもなしに、改元をやり過ごしたにすぎなかった。そこにも社会の劣化の一端が現れているが、それは明治日本が創作した近代天皇制の一帰結にほかならない。現代日本の閉塞を形づくる1つ目の文脈として新自由主義化を指摘するのが第2章だとすれば、もう1つの文脈としての特殊日本的事情=近代天皇制を指摘するのが第3章である。
沖縄と日韓・日朝関係
第4章では沖縄と日韓・日朝関係を取り上げる。戦後日本の「平和と繁栄」のバックヤードが沖縄と朝鮮戦争(およびその帰結としての南北分断の固定化)であった。したがって、戦後レジームの破綻・崩壊は、本土と沖縄との関係、日韓・日朝関係の不安定化や緊迫において劇的に表れる。その緊迫の諸相を考察することは、戦後の本質に対する私たちの理解に資するところ大であるはずだ。
第5章は、「歴史のなかの人間」と題した。ここで「歴史」を口にするのは、そこに私たちの「再生」が懸かっていると私が考えるからだ。私たちはいかにして今日の苦境を脱け出し、よりよき未来への希望を懐けるのか。キーワードとなるのは「歴史」と「記憶」だと私は思う。
現在の権力は、最悪のかたちで記憶を利用している。「東京五輪2020」と「大阪万博2025」というのがそれだ。戦後の終わり、戦後レジームの崩壊的解体の混迷に対する処方箋として戦後の発展の栄光の記憶を持ち出すことにより、さらなる「否認」の泥沼のなかで人々を眠り込ませようとする一方で、その内実はイベントにかこつけた公金の分捕り合戦にすぎない。この現実は、現代日本における良き未来への想像力の枯渇を示して余りある。
私たちの想像力を豊かにするような歴史と記憶の想起はいかにして可能か。ごく近い現代史から戦中の時代に至るまで素材を求めて試みた論考が5章に収められている。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW